ArtAnimation私的調査室
(アートアニメーション私的調査室)
2005/04/17 Ver.0.3
アートアニメーション(ArtAnimation)の分類 3
●切り紙アニメとは何か
アートアニメーションを知らない人々にとってセル画や人形アニメに比べて馴染みが薄いのが切り紙アニメーション(カット・アウトアニメーション)だろう。
切り紙とはもっとも単純なものは切った紙で作った、関節が自由に動く操り人形を思い浮かべて頂けば良い。その切り紙操り人形を背景の上に置いて各部分を少しづつ動かしながら一コマ一コマを撮影していく方法である。
旨く作られた切り紙アニメーションはセル画アニメーションもしくは動画アニメーション以上の映像の質を持たせることが出来るし、あるいは人形アニメのような雰囲気を濃厚に出させることも出来る。
 |
| ユーリ・ノルシュテイン作品集 |
切り紙アニメーションの歴史については私は詳しくないが、2005年現在、切り紙アニメーションの中でもっとも有名なのがロシアのユーリ・ノルシュテインである。というよりも、ユーリ・ノルシュテインは2005年現在、恐らく日本ではもっとも名高く、また注目されているアートアニメ作家かもしれない。
すなわち、アートアニメーションを語るときにおそらく彼の作品を抜きに語ることは(日本では)あるまい。
実際、アニメのプロ達からのアンケートで作られた参考図書『世界と日本のアニメーションベスト150』では彼の作品がなんと1位と2位を占めてしまった。
その一位と二位とは『霧につつまれたハリネズミ』(1975)と『話の話』(1979)である。
ユーリ・ノルシュテインの作品の特徴はまずその切り紙アニメとしての精緻さにある。その精緻さは一見して切り紙アニメとは分からないほどだ。というのも彼の切り紙アニメはキャラクターの部位を何十にも分け、少しづつそれぞれの位置を置き換えながら撮影しているのである。それはまさしく「芸術」と呼ぶに相応しい神秘的な出来になっており、内容とも合わせて非常に詩的な作品になっているのだ。
その内容(ストーリー)であるが、『霧につつまれたハリネズミ』と『話の話』では若干違っていて、『霧に〜』の方は擬人化したハリネズミの、ほのぼのとしたストーリーが展開する物語。一方で『話の話』ははっきり言ってしまえばストーリーがなく、いわばノルシュテインの子供時代の思い出などを、夢の中でぼんやりと思い浮かべるような作品である。
私の個人的には「わけは分からないのだけど何か、どこか心地いい」感じのする『話の話』が好きである。
ノルシュテインの作品は「詩情豊かな」作品と評されることが多いが両者ともその言葉がピッタリである。
それにしても前述のように『世界と日本のアニメーションベスト150』でユーリ・ノルシュテインの作品が1,2位を占めていたときは正直驚いたし、その後、ネット上であちこちで見かけるノルシュテイン絶賛の評も少々びっくりした。
私がノルシュテインの作品を知ったのは1993年頃以前で、オフシアターで見、確かになかなか惹かれるものがあり、1994年の戌年(いぬどし)には『話の話』に出てくるオオカミ(を犬に見せかけて)年賀状を作ったのを覚えている。
その当時、私は特に他のアニメファンとも交流する機会などなかったので、他人のノルシュテインへの評判は知らなかった。
これらの作品、というよりもユーリ・ノルシュテインを日本に知らしめる役割を果たしたのは、宮崎駿とともにスタジオジブリを築いた高畑勲 (*)だったのではないか、と私は思っている。
当時、ノルシュテインに関する本はアニメージュ文庫の『話の話』くらいしかはノルシュテインの作品について読める日本語の本はなかったはずで、その本での高畑勲の絶賛ぶりといったらこれ以上ないくらいであり、しかも当時は実際に鑑賞できる機会も多くなかったためか、写真入りで詳細に『話の話』の全てのストーリー(といっても前述のようにストーリーはないのだが)が紹介してあった。
また他でも機会ある毎にノルシュテイン作品を紹介していたようである。
ユーリ・ノルシュテインの作品としてその他にも
『25日・最初の日』(1968)
『ケルジェネツの戦い』{ただしイワノフ・ワーノとの共同監督}(1971)
『狐と兎』(1973)
『あおさぎと鶴』(1974)
などがある。
*高畑勲についてはポール・グリモーの『王と鳥』のところでも触れたが、彼はアニメーション作家で宮崎駿とともにスタジオジブリを築いた重要な人物である。というよりも、一番大きい功績は彼が宮崎駿に与えた各種の影響かもしれない。
現在、世界に知られたアニメ界の巨匠・宮崎駿であるが、彼よりは高畑勲の方がアニメ作家としては有名であった。宮崎駿と高畑勲は「東洋のディズニー」を目指して颯爽と立ち上がった東映動画に入社して知り合ったのを機会に、その後、ほとんど歩みを一緒にする。
高畑勲の作品はTV作品が多いが、具体的には
『太陽の王子ホルスの大冒険』(1968)
『アルプスの少女ハイジ』(1974)
『母を訪ねて三千里』(1976)
『赤毛のアン』(1979)
『じゃりんこチエ』(1981)
『セロ弾きのゴーシュ』(1982)などがある。その真面目で緻密なリアリティある生活描写は、「漫画映画」「子供向けTVアニメ」作品が、単なる『娯楽』として、その場で笑い飛ばして終わるだけのものから、じっくりと鑑賞し、また(大人も子供も)アニメから真摯なメッセージを受け取る価値のある作品に変貌させた。
もともと宮崎駿のもっとも得意とするのは「スリル・アクション」と言った類のものであり、たとえばその典型は『未来少年コナン』(1978)の中の冒険活劇、あるいは『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)である。
きつく言えば「ワクワクドキドキしながら、笑って見終わって、はい、それで終わり」という作風であったが、それに深みを持たせることを教えた(あるいは宮崎氏が学んだ)のが高畑勲氏であった。『風の谷のナウシカ』(1984)、『天空の城 ラピュタ』(1986)が単に冒険活劇で終わっておらず、内容的に多くの人々の心を揺さぶり感動させたのはそのような要素があったからであり、その後の宮崎駿の作品は基本的にその路線すなわち
「冒険活劇で観客を楽しませながら、どこかにその時代時代に合わせたメッセージを込め、人々の心に何かしら余韻を残し、また考えさせる」
を走ることになり、成功の道を歩む。私が思うに高畑勲氏がいなければ「アニメ界の巨匠・世界のMiyazasaki」は存在しなかったであろう。
だがそのように宮崎駿が高畑に学ぶところ大だった一方で、高畑勲氏はある種、頑なに自分の「真面目で堅い」作風を変えなかった。『〜ラピュタ』の時にスタジオジブリが立ち上がって以後、ジブリで『おもいでぽろぽろ』『平成狸合戦ぽんぽこ』を作って行くが、すでにその段階で宮崎駿の名前は高畑の知名度を圧倒しており、ジブリのプロモーション戦略では「高畑勲の作品」を強調するよりも「宮崎駿が関係している」ことをアピールして観客を集めようとする、半ば騙し的な戦略が取られた。
観客各人が宮崎駿と高畑勲の作風のどちらを好むかはともかく、このように両者を一緒にしてきちんと分けなかったことはジブリ好きにとっても高畑勲にとっても不幸なことであったろう。
●ユーリ・ノルシュテインに見るアートアニメーション作家達の苦境
アートアニメーション作家にありがちであるが、彼の作品は数としては決して多くない。
しかもこれは別項で述べるが、社会主義国はアニメーションに対して芸術・教育の観点から比較的豊富な支援を行っていた事実があり、旧・ソビエト社会主義共和国連邦も例外ではなかったのだが、1991年にソ連が崩壊してしまい、ロシアは「アートアニメ」どころではなく、ノルシュテインも食うや食わずの状態になったと読んだ。
だから高畑勲を始めとしてノルシュテインを既に高く評価していた人々は、彼の制作活動をなんとかして助けたい意図があったに違いなく、特に声を振り絞って素晴らしさを訴えたかったのだろう。
そんなこんなで日本ではすっかりアートアニメーションの代表くらいにまでノルシュテインは有名になってしまった。またノルシュテインの制作を支援する動きも活発で、ノルシュテイン・川本喜八郎・鈴木伸一など35名もの(ノルシュテイン以外?)日本人のアートアニメ作家による連作アニメ「冬の日」なども発売されている。
それくらい有名であるから、これ以上詳しくはGoogleの検索結果「ユーリ・ノルシュテイン」ででも調べて頂けば良いだろう。
ユーリー・ノルシュテインの以上のような作家活動は、ある種、アートアニメーション作家の典型(いや、ある種、幸福な場合であるが....)と言えるかもしれない。
最初に述べたようにアートアニメーションの特徴としては単独あるいは少人数での製作によってその個性が強く発揮される点に一つの特徴があるわけだが、アニメーションという手法上、多くの作品を作ることは困難であり、その結果、非常に商売にならない。極端な話、それでは喰っていけない可能性が高い。
自分のアニメで喰っていこうとすると商業化のラインに乗せるしかなく、そうなると少なくとも数年毎に作品を作って行かねばならぬ。ところがアートアニメーションに属するような作品はそんな続々と作れるものではないので、どん詰まりになる。
となると一人で作ることを諦め、プロダクションを作って大規模に進めていく、すなわち商業化に乗せようとするわけだが、しかしそうなると「個性の発揮」はしにくくなる。
アートアニメーション作家(あるいはアートかはどうであれ、自分の個性を発揮したいと思っているアニメ作家)には常にこのようなジレンマがある。
アートアニメーションの歴史を見るとき、それらの作家達は多作な人はむしろ少ない。おそらく、特に資本主義国ではユーリ・ノルシュテインが陥ったような苦境に近い立場になり、アニメ製作の継続を断念した人も多かったに違いない。
ノルシュテインの立場もさることながら、過去のそれらの人々に思いを馳せると共に、世界に散らばるであろう優秀なアートアニメ作家達が満足の出来る製作環境に置かれること、作品に見合った評価と待遇を与えられることを願うばかりだ。
●世界各地のスタジオで転々と作品を作っていたルネ・ラルー
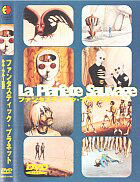 |
| ファンタスティック・プラネット |
切り紙作品としてはノルシュテインに加えてもう一作品(一作家)紹介したい。
それはフランス出身のルネ・ラルー(1921-2004)監督の『ファンタスティック・プラネット{未開の惑星}』(1973)である。
この作品はステファン・ウルの『オム族がいっぱい』というSF小説(というか、未読だがファンタジー小説だろうか?)を原作として、作家・画家のローラン・トポール{ロラン・トポール}と共同で製作を始めた作品である。が、製作開始早々、二人は衝突し、トポールは投げ出してしまったようだ。しかしルネ・ラルーは彼と似たような絵を描く画家をスタッフとして採用し、製作を続けた。
興味深いのはこの作品を制作したスタジオがプラハのトルンカ・スタジオすなわちイルジ・トルンカ(前述)が作り上げたチェコのスタジオで製作されたことであろう。ルネ・ラルーもローラン・トポールもフランス人であるため、この作品はフランス=チェコの共同作品とされている。
さて、この作品『ファンタスティック・プラネット』であるが....
とにかく奇妙だ。というか、私はこの雰囲気がゾクゾクするくらい好きなのだが、とにかく奇妙で素晴らしい。
まず面白いのは絵柄である。これは(途中で投げ出してしまったとはいえ)何よりも画家ローラン・トポールの功績が大きいのだろう。
アニメーションは「見せる」表現手法であるから、どうしても「見た感じ」の印象に左右される部分が大きい。その点で、セルアニメはどうしてものっぺりとした絵柄で、ある種、どんな絵柄でも似たような雰囲気になってしまうところがある。それに対してこのローラン・トポールの絵は、本当に独特な雰囲気を持つ。
そして重要なのはその絵を活かす為に「切り紙アニメ」を使ったことであろう。前述のようにセル画ではのっぺりとした絵になってしまい、普通の絵のような質の高さを維持することが出来ない。
ディズニーにも影響を与えている、日本の商業アニメスタジオの、宮崎駿率いるスタジオジブリの作品は非常に質の高い画面なのだが、それでもセルアニメとしての限界は出ていない。
宮崎氏のアニメは質を高く見せるために背景を極力丁寧に書くことで補おうとしてきた面があり、『天空の城ラピュタ』(1986)、『となりのトトロ』(1989)などの作品の背景はそれだけで「絵」になるほどの素晴らしい描画なのであるが、悲しいかな、背景がリアルになればなるほど「動画」であるセル絵の部分が浮き出てしまう。
『ファンタスティック・プラネット』ではそれを「切り紙アニメ」という形で違和感なく背景と動画をマッチさせているのだ。
私は最初、それに気が付かなかった(というか意識しなかった)のだが、『ファンタスティック・プラネット』を見てしまうと、その後、セルアニメでの背景と動画にどうしても違和感が見えてしまい、仕方がない。
その点だけでも『ファンタスティック・プラネット』は一見の価値があるように思う。
次に優れているのはそのストーリーの奇抜さであろう。私は原作を読んでいないので、これがステファン・ウルの作品であるお陰なのかは分からないのだが、とにかくストーリーとしての珍妙さが優れている。
私が良いと思うのは奇抜と言っても(私としては)ギリギリ論理的な範囲に収まっているように思える点だ。SFやファンタジー作品の奇抜さの中には「なんだこれ〜っ」というような、一線を越えてしまっている作品も多い。
これについては直ぐにあとで述べよう。
最後にだめ押しはやはり音楽であろうか。上で述べたような、独特の絵柄と動き、ストーリーの奇抜を、それらをどんよりというか、ぐわんぐわんというか、後ろで流れる音楽が非常にうまく支えている。
参考図書『世界アニメーション映画史』でもこの作品を「大人向きの良質なファンタジーとしてアニメ映画史上類をみない作品だ」と評している。
 |
|---|
| ルネ・ラルー傑作短篇集 |
さて、ルネ・ラルーには他にも作品があり、『ファンタスティック・プラネット』より以前、ローラン・トポールと決裂する前に彼と共同で作り上げた短編が『死の時間』(1964)と『かたつむり』(1965)年である。
『死の時間』に関しては未見だが、『かたつむり』に関してはDVD『ルネ・ラルー傑作短編集』に入っている。
『かたつむり』のストーリーもかなり奇妙奇天烈、というか『ファンタスティック・プラネット』以上に奇抜で、それなりに楽しいのだが、如何せん、技法的なことについては『ファンタスティック・プラネット』と比べようもないくらい、単純というか、実験段階的なものであり、「パラパラ漫画」「パラパラ絵画」「紙芝居」という感じに止まっている。(いや、無論、これだけ動かすのも大変なことは分かるのだが....)
まあ面白いことは面白いのだが『アニメーション』としての感動はちょっとしにくい。
それに対して『ワン・フォはいかに助けられたか』(1987)はルネ・ラルーのほぼ最後の短編作品であり、実験的なものではない。ただしこれはセルアニメである。これについては後の『ガンダーラ』の作品のところで述べたい。
さて『ファンタスティック・プラネット』の素晴らしさを述べた際、ストーリーに言及したが、同じルネ・ラルーの作品でも、なんだかちょっと理解不能なまでのストーリー展開をしてくれちゃうのが『時の支配者』(1980)である。
まずこの作品の特徴は、その漫画家として世界的に有名な(と言うか米国とヨーロッパでか?)メビウス{ジャン・ジロー}を原画と脚本に迎えていることである。
この作品は『ファンタスティックプラネット』と違って、日本でもお馴染みのセルアニメであり、しかもメビウスの絵ということもあって、のっぺりした、ある種、アメコミ的な映像になっている。それでもメビウスの絵柄はまだどこかに暖かみがあるように思われ、日本人にもそれほど受け入れるのに難しくはないのではないか。
だが、ストーリーは....かなり分けが分からない、というのが正直なところだ。
勿論、オチは分かるのだけれども舞台の背景が一見、SFすなわち今の私たちにもある程度理解できる(というか納得の出来る?)世界観かと期待させるのに対して、ストーリー展開がそれから外れていってしまい、わけわからない感じになってしまっているのだ。
冒頭のなかなか格好いい始まりといい、それなりにユニークなキャラクターといい、面白い要素はあるのだが....
なお、この作品が作られたのはハンガリーの首都・ブタペストにある「パンノニア・フィルム・スタジオ」というところである。
ルネ・ラルー作品の興味深い点の一つは『ファンタスティック・プラネット』(1973)の時のトルンカ・スタジオ(チェコ)、『時の支配者』(1980)のパンノニア・フィルム・スタジオ、そして次の『ガンダーラ』(1988)では朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の平壌のスタジオで作られていることであろう。
 |
|---|
| ガンダーラ |
『ガンダーラ』(1988)はルネ・ラルー監督の3番目・最後の長編である。フィリップ・カザをデッサン(キャラクター・デザイン?)として迎えているが、これもやはりセルアニメだ。
カザの絵柄はメビウス以上にアメコミ(アメリカ・コミック)調らしく、残念ながらこの作品の絵柄と動きは、最近の日本の技術と緻密さの高いセルアニメを見慣れていると物足りなさを感じるかもしれない。
ストーリーは...まあ奇想天外ではあるが、全体的には無難なファンタジー系作品、という感じに収まっている。
ちょっと驚いてしまうのは登場する「フリークス」すなわち奇形達である。
日本ではあまり知られていないが、各種の身体的奇形は一定の割合で発生するとされ、特に欧米では一時期まで見せ物小屋の「スター」として活躍してきた。この『ガンダーラ』に出てくるフリークス達は極端にそれを強調したものであり、たとえば首から上が全くないとか、顔が5つも6つもついているとかは私も聞いたことがないが、体の途中からもう一人の下半身が生えていたり、指が6本だったり、足が三本であったり、双子で体がくっついている(頭や腰など)場合などの人々は存在する。
日本でも『五体不満足』の著で有名になった乙武洋匡氏も「先天性四肢切断」という先天的身体奇形障碍である。
また、先天性奇形の一パターン・結合性双生児については日本ではベトナム戦争によると思われるベトちゃん・ドクちゃんの兄弟が有名だが、そのような身体的奇形は必ずしも環境汚染などで発生するだけではなく、たとえば米国のヘイゼル姉妹が有名だ。
ともあれ、そのような人々の特徴を持った「種族」がアートアニメ、否、アニメや一般映画自体に登場し、一役割を果たすというのは極めて珍しいと思われる。
ただ作品の中では彼らは遺伝子改良の結果で出てきた「種族」という形で登場し、「中央の世界からは人間扱いされない、悲劇の人々」という扱いで描かれていて、あまり目新しくない視点というか、見方によっては先天的奇形を別種の生き物であるかのように扱う感じで、気持ちよく感じない。
スタッフの意識としては奇形障碍者への差別意識を取り除くことを意識していたのかもしれないが、彼らを身体外の異能(超能力?)の所有者として扱うなど、意図が不明な点はある。
少し話が逸れたが、まあそういう部分を含め、ストーリー的には1988年という製作年代を踏まえても、新鮮で仕方がない、というほどの作品ではない。
そういえば、私はこの作品には1984年公開された宮崎駿氏の『風の谷のナウシカ』の影響もかなりあるのではないかと感じた。この作品の前にルネ・ラルーがコンビを組んだメビウスは、娘に「ナウシカ」と名付けるほど宮崎駿氏のファンであり、ルネ・ラルーも恐らく宮崎駿氏の作品には注目するようになっていたと思われる。
ルネ・ラルーは2004年に亡くなったが日本でも以上の4つのDVDをまとめたDVD-BOXが発売されている。
なお、前述のようにルネ・ラルーは長編を三作であり、そのうち『ファンタスティック・プラネット』が切り紙アニメ以外はセルアニメである。よって国別のところで紹介したい気はしたのだが、自らはフランス人にも拘わらず、制作スタジオをチェコ、ハンガリー、北朝鮮と変えている点もあり、圧倒的に名声の高い『ファンタスティック・プラネット』を代表として、この「切り紙アニメ」のところで紹介することにした次第である。
●他のアニメ作家の切り紙アニメ
切り紙アニメは手法的に必ずしも難しい方法では無いため、アニメ作家の多くが試みているようだ。すでに人形アニメのところで述べた川本喜八郎も『詩人の生涯』という作品を作っているし、別途述べるカレル・ゼマンも晩年は切り絵アニメを専らとした。